

スクランブルエッグサンド
まだ車通りも少ない、朝の静かな時間帯。こんな早くから、焼き上がったばかりのパンとコーヒーの香りで満ちているのは、北中城村の小高い場所にあるベーカリーカフェFIFTH SON。うっかりしていると通り過ぎてしまいそうなほど、通りの景色に溶け込んでいる。
FIFTH SONは、キッチンが店舗面積の半分ほどを占めている小さな店だ。カウンター席からは店主の長嶺誠さんが立ち働く姿がよく見える。パンをスライスする。ボウルを卵に割り入れ、溶きほぐす。サラダを盛り付ける。使い終わった道具はすぐに片付ける。そのキビキビした所作と姿勢の良さに目が奪われる。すっきりと整った厨房もそこにいる長嶺さんも実に絵になる光景で、自分のための料理を作ってもらっているのだと思うと、皿が運ばれてくるのが待ち遠しくてたまらなくなる。
長嶺さんは、一見海が似合うミュージシャンのように爽やかな風貌だが、スナックのママやバーのマスターを連想させる一種独特な雰囲気を持っている。お客さんとのやり取りを見ていると、誰に対してもフラットで、カウンター越しの会話を心から楽しんでいるのが伝わってくる。適度な距離を保ちつつ、質問をされたり、意見を求められたりしたら、率直に話す。いい感じでほっといてくれるときもあれば、親身に話し込んでいるときもある。客あしらいがとても良いのだ。

食パンは1斤350円、2斤700円で販売
人間味豊かな店主と、手入れの行き届いた居心地の良い空間。どちらも行きたくなるお店の大切な要素だけど、一番はやっぱり自家製の食パン。そのまま手でちぎってみた。耳まで柔らかく、しっとりと伸びが良い。噛めば、小麦の豊かな香りとミルキーで上品な甘みが口いっぱいに広がる。柔らかくモチモチとしたテクスチャーも、とろけるような口溶けとのど越しも気持ちよかったが、心奪われたのは余韻となって残る甘みだった。
「味としては、リッチなソフト系のパンと、リーンなハード系のパンの中間あたりを狙っています。甘いけどくせがなくて、毎日食べても飽きがこない、そのまま食べてもおいしいパンが理想なんです」
長嶺さんはいわゆるリッチ系といわれる副材料を多く使った食パンを作っている。昨今の高級食パンブームの影響かと思いきや、子どもの頃から甘くて柔らかいパンが好きだったというから微笑ましい。
「沖縄で、手作りのパンを提供する朝ごはんのお店をやろうって決めてから、時間をかけて準備を進めてきました。やっと満足のいくものが作れるようになって、よしオープンするぞ! というときにブームがきたから、最初はうわー、まじかってなりましたよ(笑)」
自分好みのパンをしっかり作りたいという思いから、材料にはカナダ産一等粉、良質な生クリーム、はちみつ、生イーストなどを使用。そして、冷蔵庫に一晩置いて熟成させた生地を朝に焼き上げるオーバーナイト法で作っている。
「生イーストを使うと、香りが断然良くなるんです。アレルギー対策で卵を使うのをやめたので、その分、生クリームを多く入れてコクを出していますね。オーバーナイト法にしたのは、この製法だと小麦粉の粒子にしっかり水が浸透するし、時間をかけて発酵させることができるから。風味豊かで、ふんわり、もっちりとした仕上がりになるんです」

この食パンを看板に、長嶺さんはサンドイッチやトーストセットなどの食事メニューも作っている。その中で、ハッとするほど美味しい隠れた主役がいた。それはチキンのソテーだ。パリパリと香ばしく焼けた皮に、ふっくらとジューシーなお肉。一見普通のメニューだが、レストラン顔負けと言えるほど、味と香りのバランスが良いのだ。ローズマリーの爽やかですっきりとした香りに、芳醇な肉の旨味。噛めば噛むほど、ハーブやスパイスの風味が感じられる。トーストされたパンと一緒に食べると、チキンの塩っぱさがパンの上品な甘みを押し上げてきて、その取り合わせの良さに思わずうなり声が出た。
こういうシンプルな料理は、きちんと美味しく作るとなると本当に難しい。理由を尋ねて腑に落ちた。以前、東京で丸焼きチキンの専門店を経営していたというのだ。
「フランスの家庭料理でよく食べられている鳥の丸焼き、ロティサリーチキンを販売していました。今作っているチキンソテーの味付けは、そのレシピをベースにしているんです。ローズマリー、マジョラム、オレガノ、唐辛子パウダーなどをブレンドしたものを刷り込んで、冷蔵庫に1日以上寝かせていますね」

長嶺さんはうるま市出身。高校卒業後に上京し、それから20年ほど東京で暮らしていた。むこうでは複数の飲食店を経営し、売り上げも好調だったそうだが、なぜ沖縄へ戻って小さなお店ひとつを経営しているのか不思議に思う。
「上京した最初の頃は、建設機械の運転手として生計を立てていました。自分の店を始めたのが26歳のときです。資金がなかったので小さなフードトラックを購入し、タコスとタコライスの移動販売からスタートしました。オフィス街、フジロックやサマーソニックなどの夏フェス、大型イベントに出店していましたね。29歳のとき、フードトラックは信頼できるスタッフに現場を任せて、三軒茶屋でメキシコ料理店を構えました。フードトラック業は順調で、最初は売れて楽しかったんですけど、忙しくなりすぎてしまって…。丁寧な接客とは程遠い、スピード重視の仕事をするようになって、次第に売り上げが良くても嬉しくないし、赤字が出ても何とも思わなくなりました。こんなことを続けていていいのかと考えるようになりましたね」
メキシコ料理店はふるわず2年で撤退したが、これがきっかけとなり、長嶺さんの食への興味や関心は深まる。
「お店をやっているうちに本場のタコスのことが気になって、メキシコへ行ってみたんです。そしたら、僕が作っていたタコスがどこにもなかったんですよ。メキシコのタコスって、牛肉や豚肉、煮込み料理などのおかずを、トウモロコシの粉で作ったトルティーヤという柔らかい皮をご飯のようにして食べるんです。ナチョスやブリトーという料理もなくて、僕が子どもの頃からずっとメキシコ料理だと思っていたものは、どれもメキシコ風のアメリカ料理だったんだと分かって衝撃を受けましたね」

自家製ジンジャーエール。ローズマリー、シナモン、スターアニス、唐辛子、砂糖などを煮詰めたシロップを使用
店を畳んだ後、長嶺さんは沖縄でよく食べられている世界の料理の中から鶏の丸焼きに目をつけ、すぐに港区でロティサリーチキンの専門店『ファーマーズチキン』を開業。今でこそ、東京に同ジャンルの店は増えているが、長嶺さんの店はその先駆けだったといえる。
「タコスと同じように、鶏の丸焼きは沖縄の人の生活に浸透していたけれど、僕の知る限り、当時の東京で食べられるところはなかったし、お店をするには良いなって思ったんです。でも、沖縄で売ってる丸焼きチキンはニンニクをたっぷり使った南米の味。オフィス街のランチに、においが強い料理は出せないなって思って、鶏の丸焼きでも、フランスのロティサリーチキンでいくことにしました。フランス料理は味付けにあまりくせがないし、いろんな人に受け入れてもらいやすいだろうって。メキシコへ行ってから、トラディショナルな料理により惹かれるようになっていたので、フランスにも何度も足を運んでレシピを勉強しましたね」
フランスから輸入したロティサリー専用マシンで焼き上げたチキンは、ビジネスマンを中心に一気に火が付いた。小さなカウンター席はランチタイムになるといつも満席。テークアウト専用の窓口にも長蛇の列ができるようになるが、仕事が忙しくなるにつれ、長嶺さんにまた悩みが生じる。
「当時のランチタイムは殺伐とした雰囲気でした。列に割り込もうとする人がいたり、理不尽に怒鳴られたり、『テーブルをふくので少しお待ちください』と声をかけただけで舌打ちして帰ったりする人もいました。そういうことがずっと続くと、もうストレスマックスなんですよ。初対面のお店の人にそういう横柄な態度をとるのってどうなんだろうと考えるようになりました。海外を旅行したときに、お店の人とお客さんとの対等な関係を目にしたり、お店で雇った外国人スタッフの堂々とした態度を見たりするうちに、日本のお客様は神様文化がおかしいんだって分かってきて、意見を伝えられるようになっていきましたね」

ラスクやコーヒー豆も販売。コーヒーはペルー産のオーガニックコーヒー。村内にある安座間珈琲に焙煎してもらったオリジナル
仕事に追われる日々。次第に、休みは海外の静かなリゾート地で過ごすことが増え、ゆったりと過ごせる田舎暮らしを考えるようになった。沖縄に意識が向き始めたのもこの頃だ。
「若い頃は沖縄が狭い世界に思えて、出たくて仕方ありませんでした。でもある日、ふとTUTAYAで沖縄民謡のアルバムを借りてみたんです。そしたら止まらなくなっちゃって、返却するまでに何十回も聴きました。それから、沖縄で仕事や生活の基盤をつくれるか調べようと思って、時間を見つけては月1ペースで来るようになりました。沖縄に戻る決意を固めたのが、那覇空港でレンタカーを借りる手続きをしたときです。翌朝の東京行きの便がレンタカーの店舗の営業時間前で困っていたら、そのレンタカー店の方に『長嶺さん、あのね、だったら朝、ここの駐車場に車置いてっていいから。鍵さしっぱなしでいいから。もしぶつけたら、シートの上に5万だけおいといてね』って言われたんです。その時、やっぱり俺ウチナーンチュだ、ウチナーに住もうって思ったんですよ(笑)」

パンは朝4時台から焼き、翌日分の仕込みも同時並行で行っている。店名につい尋ねると「5人兄弟の5番目なんです。そのままでしょ」と笑顔
ウチナーンチュの気質をあらわしているような優しさ、おおらかさに触れ、長嶺さんは人生を大きく変える。店の経営は、仲の良かった常連さんに譲り、2017年9月、長い東京生活にピリオドを打った。その後、11カ月におよぶ準備期間を経てFIFTH SONをオープンする。
「一人でやっているし、パン作りは時間も労力もかかるから大変」と言いながら、試作中の新しいサンドイッチの写真や、テラスをつくる予定という屋上をうれしそうに見せてくれた。長嶺さんが望んだ通りの生活は、ここでできているのだろうか。
「これまでは夜の時間帯での仕事が長かったし、朝ごはんのお店がどうしてもしたかったんです。軌道に乗るまでにはもう少し時間がかかりそうですが、今は何もかもが楽しい。幸せのシャワーを浴びている感じですね(笑)。お客さんとの何気ないやりとりが楽しいし、朝にコーヒーを飲んでも、沖縄で飲んでいるものはとても美味しく感じる。そういうのって、幸福感からくるところも大きいと思うんですよ。これからは、もっと朝のメニューを強化して、ゆくゆくは朝のみの営業ができればと思っています。今日の朝ごはんは外でのんびり食べようっていうときに、じゃあFIFTH SONにしようって選んでもらえたら嬉しいです」
入り口のドアが開き、近くに住むおばあちゃんらしき人が入ってきた。「ここは何があるの?」。長嶺さんはメニューの説明をし、ひと言ふた言話した後、笑顔で見送った。その穏やかな表情に、こちらも頬がゆるむ。
何気ない日常が与えてくれる喜びと安心感。そして、沖縄のメンタリティ。長嶺さんはその大切さ、かけがえのなさを身をもって知っている。だからこそ長嶺さんのお店は、この土地の人々の日常に心地よく馴染んでいくことだろう。
文/徳嶺綾子
写真/金城夕奈
FIFTH SON(フィフサン)
北中城村島袋1411
050-1446-3898
open 8:00~17:00(L.O. 15:00)
close 月・火
https://www.instagram.com/fifthson_okinawa







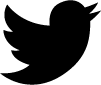












 @marph_kitchen
@marph_kitchen








