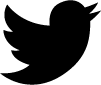夏目漱石・著 新潮社 ¥340(税別)/OMAR BOOKS
司書として学校に務めていた頃、その7年ほどの間に勤務先の図書館は5回変わった。今でもその日々でまず思い出すのは、それぞれの窓から見えていた風景だ。
たっぷりと葉を茂らせた大きな木が大半の面積を占めるのや、天気に寄って表情を変える空とそれを横切る電線、遠くまで連なる住宅の屋根、かすかに見え隠れする海。仕事用として与えられた机に肘をついてはそれらの窓の向こうの風景を前に、ずいぶんとりとめのないことばかりを考えていたような気がする。今となってはその内容はほとんど憶えておらず、あの時の自分と遠く隔たっているような、それでいてまぎれもなく今の
自分と地続きであるという不思議な心地がする。
当時病気がちだった夏目漱石が、自宅の硝子戸の中(ガラスどのうち)から外を眺めながら思い巡らせたことなどを綴った随想集『硝子戸の中』を読んでいて、図書館でもの思いに耽っていたあのときの気分をぼんやりと思い出した。
大病をした後、一日中書斎で静かに過ごす生活の中で、気の向くままに身辺の出来事を率直に綴った漱石最後の随想集とされる本作。飼犬へクトーや猫たちのこと、新聞に連載していた漱石の小説の読者だという女性たちや図々しい読者とのやりとり、社交について思うところ、芝居を見に行ったときの友人との言い合いなど、思いつくままに語られていて、読んでいるうちに文豪・漱石がとても身近な存在に感じられてくる本だ。
久しく会っていなかった友人と出かけ、電車の中でその友人がハンカチの中から栗まんじゅうを取り出してみせたとき、自分が驚いたことを思い出す、という章がある。自分の心が動かされたこういう小さな、何気ない一コマを漱石はひとつひとつ取り出して見せるが、後半では次第にその多くが過去の話にも繋がっていく。
「時は力であった」
とこの中で書かれているように、この『硝子戸の中』で語られる作家自身の人生、他人との関係、社会との関わり方や生と死が、「時」の力によって変化していく様が夏目漱石という透徹したフィルターを通して読む側に静かな安穏をもたらしてくれる。何故ならいくら変化しようとも、過去から続く「時」は途切れることなく続いているから。
漱石作品は小説しか読んだことのない方にもぜひおすすめしたい一冊です。
OMAR BOOKS 川端明美![]()

OMAR BOOKS(オマーブックス)
北中城村島袋309 1F tel.098-933-2585
open:14:00~20:00/close:月
駐車場有り
blog:http://omar.exblog.jp