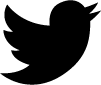川上未映子・著 新潮社 ¥1,500(税別)/OMAR BOOKS
平日の夕暮れ時になると、小学生の姿がぽつぽつと店の前を横切る。
ピンクのランドセルを背負って一人とぼとぼ歩く女の子や、互いにぶつかり合ってはくっついて歩く三人組、自転車にまたがったまま大声で会話する男の子たち。「お前の気持ち次第でいいってば。」気持ち次第って何が?聞こえてくる彼らの話にツッコミを入れながら、ああ、私はもうあちら側の世界にはいないんだなあと少し寂しい気分になる。確かにあの場所に私もいたのに、いつのまにか押し出されてしまった、と。
今回ご紹介するのは、「ミス・アイスサンドイッチ」「苺ジャムから苺をひけば」の二章から成る川上未映子さんの最新長編小説『あこがれ』。
言葉を交わしたこともない、スーパーでサンドイッチを売る女性に、淡い感情を抱く小学生・麦彦の日常を描く前者と、麦彦の同級生で、亡くなった母親から受け継いだ苺ジャムを作り続ける父親の秘密を
知ってしまう女の子ヘガティーの成長を描く後者。
いつもスマホをいじって息子には無関心に見えるスピ系の母親よりも、言葉をほとんど失ってしまった認知症の祖母に親しみを抱く麦彦。彼は異質の存在、ミス・アイスサンドイッチへの自分でもよく分からない感情を持て余し、それを受け止めるヘガティーは一年中片付けられることのないクリスマスツリーをいつも見上げながら眠りにつく。
小さな孤独が互いを支え合うユートピア。
この小説には誰もがいつか通った場所が描かれている。生と死に近いところに無防備でいたあの頃。家族であっても、どんなに身近にいても他人のことは分からない。自分が感じていることも他人には本当には分からない。“はじめて”他者という存在に出会う驚き。知らなかったことを知っていくこと。大人になるというのは、知らなかったこれまでの自分にさよならし続けていくことで、それが生きていくことなのだろう。
「あこがれ」を持ち続けることは案外難しいのかもしれないのかもしれない。少なくともあの頃のように無邪気にという意味では。
「手をふりながら、なぜだかわたしは、今日のことは忘れないだろうなとそう思った。」
ヘガティーの心の中のつぶやき。一回性の、そういった個人的な記憶こそが、その後のその人の人生を支える。失われてしまった大切な時間を愛おしく描いた小説。おすすめです。
OMAR BOOKS 川端明美![]()

OMAR BOOKS(オマーブックス)
北中城村島袋309 1F tel.098-933-2585
open:14:00~20:00/close:月
駐車場有り
blog:http://omar.exblog.jp