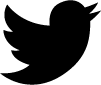「今回の舞台では、組踊で使われる笛の音をフルートで奏でることにしました。琉球音楽とクラシックを繋ぐ接点になれるのではと考えたのです。
琉球音楽とのコラボレーションは、これまでも色々な形でなされてきたと思います。しかし、クラシックとのコラボとなると両者をしっかりと生かすのがなかなか難しい。
なぜならば、どちらも『古典』だからです。
それぞれが文芸作品として成立している両者を公平に、本当の意味でコラボレートさせるのであれば、新たなベースを作らなければなりません。
でも今回は新たな作品を作るのではなく、それぞれオリジナルをしっかり聴いていただこうと考えました」
ドイツ、ウィーンで研鑽を積んだフルーティストの渡久地圭さんは、2012年から活動の拠点を自身のふるさとである沖縄に移し、さまざまな方法でクラシックの魅力を伝える試みを行っている。
組踊音楽歌三線人間国宝の西江喜春氏、プラハ国立歌劇場で主役を務めたソプラノ歌手の豊嶋起久子(てしまきくこ)さんらを招き、同じ舞台で琉球古典音楽とクラシックを演奏する公演「献歌」を12月5日に開催したばかりだ。
クラシック音楽の楽しみ方や琉球古典音楽とのコラボの方法、また、渡久地さんの活動などについて幅広くお話を伺った。

「日本でどうやって活動していけばクラシックがより広まるかということについて、(豊嶋)起久子さんといつも話しているんです。
起久子さんは能楽・金剛流の生まれであることもあり、日本の伝統的な芸術・芸能とのタイアップについても話題に上ります。
日本人である僕らが、クラシックというよその国の芸術をやっているわけですが、『僕ら日本人じゃん、ウチナンチュじゃん!』という思いはありますし、日本の芸術をリスペクトする気持ちは強いんです。
これからは、そういう想いを大切に持ちつつ、両者がお互いに歩み寄って刺激を受け合うという流れが必要じゃないかと思うんです。
クラシックというとある程度イメージが定着しているというか…。ちょっと敷居が高いというような雰囲気がどうしてもあると思うんです。
また、そういう風に感じさせてしまっている原因は、クラシックをやっている当事者にあるんじゃないかという気もしていて。
もちろん、素晴らしいものだという確信があるからこそクラシックをやっているのですが、それを日本の皆さんに伝えていくのはなかなか難しい。
もともとが外国の文化だから、馴染みが薄いという大前提があって、そこをどう突破していくかが課題だと思うんです。
そこで、一つの方法として沖縄の伝統芸能とコラボをしてみるのはどうかな?という案が浮かびました。それも普通のコラボではなく、どちらもぞれぞれ質の高いものを一つの舞台でやろう、と。
これまでも色々な形でのコラボはあったと思うのですが、こういう形はなかったと思います」
その時、渡久地さんの頭には一人の人物が浮かんでいた。2011年に人間国宝に認定された西江喜春(にしえ きしゅん)先生だ。

「きっかけは、NHKで放送されたドキュメンタリー番組。人間国宝に認定されたということで先生のご活動を特集した番組が放送されていたのをたまたま観ていたのですが、『この方すごい!…すごいぞ!』と感動しました。
とりわけそのお声にすっかり魅了されたんです。非常に張りのあるお声で、何しろ素晴らしくて」
偶然にも、渡久地さんと西江先生との間に共通の知り合いがいることがわかり、企画と想いを伝えることができた。
「僕は起久子さんの声はよく知っているし、ヨーロッパでもオペラ座で主役を歌われたほどの実力と才能の持ち主。また、その舞台も観に行って歌声を聴いていたのでイメージはできていました。そこに西江先生の凛としたあの歌声が入ったらこれは素晴らしい舞台になると確信したんです。
先生は人間国宝に認定され、僕らが想像できないような制約もあるのではないかと懸念もありましたが、ご承諾くださって。
沖縄にもこんなに素晴らしい方がいらっしゃって、こういう伝統芸能があるんだということを、ウチナンチュとしてはやっぱり大きな声で言いたかったんです」
西江先生の歌声のとりこになったのは渡久地さんだけではない。
舞台「献歌」のリハーサル時、西江先生の生の歌声を聴いたソプラノ歌手・豊嶋起久子さんも驚嘆の声をあげたという。
「『あの歌声は…素晴らしいテクニックだね』と。音を集中させる発声のテクニックがあるそうなんです。先生に実際に伺ったわけではありませんが、それを実践されてるのかな、と」
西江先生の歌声は「飴色の声」と称されている。
伝統芸能の歌声というと、重厚で落ち着きのある、どっしりとしたイメージを持っていたのだが、最初の一声でそのイメージは覆された。
雲一つない広々とした晴天の空に、細く鋭い矢がまっすぐに、どこまでも飛んでいくような勢いがある。
艶があり、きわめてソリッドな声。
そして、どの歌を歌っていても感じる陽性の響き。
心のくもりをさっと払うような清々しさ。
このままいつまでも聴いていたい。聴く人すべてを魅了する、特別な歌声。
リハーサル時、西江先生率いる組踊チームの演奏が終わると、クラシックチームからは感じ入ったように
「素晴らしい、本当に素晴らしい」
という賞賛の声と拍手が聞こえた。

舞台では、組踊の演目「手水の縁(てぃみじぬいん)」より、「忍びの場」が披露された。
主人公・山戸(ヤマトゥー)が 再会を誓った玉津(タマチィー)の家に忍んで行くシーン。山戸が吹く笛を、沖縄の笛ではなく渡久地さんがフルートによって演奏する。
「今回の舞台で、琉球音楽とクラシックが最も接近するシーンです。
僕の存在自体、ウチナンチュでありながらなぜかフルートをやってるということで、二つの世界をつなぐ役目を果たせないかなと考えました」
そのシーンを観ていると、とても不思議な気持ちになった。
琉球装束を身につけた立方(たちかた:踊り手)が笛を吹く仕草に合わせ、渡久地さんの奏でるフルートの音が響く。
違和感はまるでない。その澄み切った音は組踊の世界に難なく馴染み、主人公の想いをしっかりと代弁している。
渡久地さんのフルートの音色は、組踊の世界に馴染ませるための細工が施されているようには聴こえない。あくまでもクラシックの楽器というフルートそのものの音色をもって、組踊にアクセスしているように感じた。
三線、琴、フルート、そして西江先生の歌声。
すべてがお互いを尊重しあい、引き立て合っているからこそ生まれる、特別な響きに包まれた。
「日本の伝統芸能とクラシックは、お互いに歩み寄って刺激を受け合うという流れが必要」という渡久地さんの言葉が実践されていることが、その響きからありありと感じられた。

渡久地さんとフルートとの出逢いは、小学校三年生にまでさかのぼる。
「出逢いはね…今考えてもおかしいんですけど、音楽の教科書の写真がきっかけだったんですよ。
僕は本部(もとぶ)の出身なのですが、当時はまわりにフルートなんてなくて、実物を見たことも音を聞いたこともなかったんです。
だけど小三の音楽の教科書をめくったら、裏表紙に楽器の写真が一覧表で掲載されていて。トランペットとかヴァイオリンとかね。そこにあったフルートの写真を見て『これやりたい!』って。…そう、ビジュアルだけで(笑)。
でも実物がなかったので、リコーダーにストロー突っ込んで横にして吹いてみたりしてました(笑)。それだけフルートに想いを寄せていたんです。
こんな子ども、もちろん他にはいなかったですね(笑)」
四年生になってブラスバンド部に入部するも、金管バンドだったのでフルートはなくトランペットを吹いていたという。そして五年生のとき、ついに実物を手にすることになった。
「両親が買ってくれるというので那覇まで行ったんです。那覇高校の前の『文教楽器』という店で。よく覚えていますよ。
それまで吹きたくて吹きたくてしょうがなかったから、僕ね、買ったその日に一曲吹いたんですよ。指使いはすでに運指表で覚えていたので。ちょうどいとこの入学祝いがあったので『思い出のアルバム』という曲を。『いーつのーことーだかー』っていうアレです。
それにしても、どうしてあんなにフルートに思い入れが強かったんでしょうね。今でも不思議なんですよ、あの感覚は。
小三で出逢ってからずっとフルート一筋、浮気なしです」
中学生の頃にはすでに音大受験を視野にいれ、開邦高校芸術科音楽コースに進学した。
「当時は高校にフルートの先生がいらっしゃらなかったので、授業が終わってからバスに乗って那覇市若狭の教室まで通っていました。
僕は寮に入っていたのですが、門限が6時、7時には食事が終わり、7時半にはお風呂にも入れなくなるという厳しさ。でも僕はフルートの勉強のために出ていたので特例扱い。たまにちょこっと寄り道して帰った思い出もあります(笑)」
卒業後は武蔵野音楽大学に進学した。恩師の留学先がドイツであったり、恩師の知り合いにドイツ系の演奏家が多かったことなどから、ドイツ留学を検討するようになったと言う。
「大学卒業後、何のあてもなく、学校も決めないまま『とりあえず行こう!』とドイツへ行っちゃったんです」
語学学校に通いながら先生を見つけ、大学の入試を受けて入学した。
その行動力にも、「どうにかなる」という楽観性にも驚かされる。
「基本、ノンカー(=のんき)なんですよ(笑)」
ドイツで4年半研鑽を積んだのち、ウィーンに渡った渡久地さんは、ウィーンフィル首席奏者のマインハルト・ニーダーマイヤーに師事し、フルート奏者としての仕事も始めた。
「それと同時に沖縄・日本とウィーンを行き来するようになりました。沖縄でやりたいことも膨らんできていたんです。
この素晴らしいクラシックを日本でもっと身近に感じてもらえるにはどうしたらいいか、本当に質がよく、聴いていて楽しいと感じられる音楽を紹介していくためにはどうすればいいかということを、自分で考えたり、起久子さんと話したりするようになりました」

沖縄には、様々な音楽を受け入れる土台があるように感じると、渡久地さんは言う。
「開かれた感受性を持っている感じがするんです。反応も素直でストレートで。だから、質の良いものを聴いていただける場をたくさん作れば、『クラシックって良いな』と感じていただけるんじゃないかな? と。
クラシックの普及活動の一環として、おしゃべりもするコンサートを各地で行っているんです。クラシックって姿勢正してしっかり聴かなきゃーっていうイメージがあるでしょ、咳もしちゃいけないとか(笑)。そういうイメージをできるだけ取り払って、フランクに聴いていただける場を作りたいと思っていて。
すると、そういうコンサートでこちらから語りかけたときの反応は沖縄が一番良い気がするんです。舞台とお客さんとの距離が近いというか。緊張しすぎることなく、のびのびと音楽を楽しむ感受性が備わっているように感じます。
沖縄って色々な可能性を秘めた土地だと思うんですね。色々なシーンでもう少し沖縄が頑張れたらなーと、ウチナンチュとして期待を寄せています」
また、フルーティストして、自身が求める音色を奏でるための努力も忘れない。
「僕が好きな音色は、なんていうのかな…混じりっけのない音。
もちろん、フルーティストとしてはパレットに様々な色があるのが良いんです、こんな音も出せる一方であんな音も、というのが理想。
でも僕は、ニュートラルな音への理想があるんです。澄みきった音。それでいて輪郭としての縁はあって、その輪郭の中は音で満ち満ちている。固く、キュッというのでもなく、ほわーんっていうのでもない。丸くてボーンっと響く音。
その理想を実現できるよう日々努力していますので、徐々に近づいているように感じています」
渡久地さんは音楽以外の文化面においても、沖縄の環境がより整えられたらと考えている。
「音楽に限らずなんでも、大切にリリースされたものって『お!』って思うじゃないですか。
食もそう。おいしいものを食べたいなーって思ったとき、少し値段が高かったり量が少なめだったりしても、『いいね〜』って共感できる人や場が増えたらいいなって。
そういうことは様々な分野に共通して言えると思うのですが、僕らはクラシックをやっているので、良い音楽をお届けするためにこれからも努力して、環境を整えていくお手伝いができたらと思っています。
12月22日には、OIST(沖縄科学技術大学院大学)でクラシックの名曲を演奏する機会をいただきました。みなさんどこかで耳にしたことがある曲ばかりだと思います。
予約は必要ですが入場は無料。子どもさんたちにも是非来ていただきたいですね」
顔を合わせれば冗談を言い、終始笑いが絶えない三人はいずれも、世界を舞台に活躍しているアーティストだ。
その演奏や歌を聴けば、普段クラシックを聴く機会の少ない私でも、質の高さを瞬時に感じ取ることができる。
また、CDやパソコンといった媒体を通して聴く音と生の演奏とでは、当たり前だけれど音の響き方がまったく違う。
最初の一音で、瞬時に心臓をぐっと掴まれる。それも戸惑ってしまうほど直接的に。
気づいた時には、心と意識が別世界へと飛んでいる。耳に届く音が、見たこともない景色へといざなってくれる。
そのすべてが一瞬の出来事で、知らず知らず目には涙があふれていたりする。
そういう体験はきっと、上質でリアルな音楽だけがもたらすことのできる効果の一つだろう。
からだに良いものを食べようとするように、良いものを聴こう。
私たちのまわりにはその機会が、環境が、整えられ始めている。
写真・文 中井 雅代
渡久地圭
ブログ http://nufa.ti-da.net

クリックで拡大します
詳細はコチラ