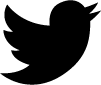小ぶりでころんとした可愛らしい豆大福。その餡は、引き立て役。塩気がしっかりときいていて、歯ごたえある赤えんどう豆の自然な甘さを際立たせる。
こんがりとした焼き色が食欲をそそるどら焼き。その餡は、ダブル主演の片方。小豆の粒感が舌に心地のいい餡は、他方の主役のふんわりヌチっとした皮と、よく調和する。
鮮やかなピンク色が春を感じさせる桜餅。その餡は、控えめな脇役。桜の華やかな味や香りのじゃまをせず、そっと味覚の下地をつくる。
「あんこ」と一口にいっても、その菓子によって味や表情は様々。あんこの役割って、和菓子ごとに異なるのだなと思わず唸る。餅や皮との組み合わせや歯ごたえのバランスが、どれをとってもすこぶるいい。職人のそんな細やかな仕事を感じさせるのが、羊羊の和菓子たち。

この和菓子、つくっているのは意外にもスタイリッシュな男性二人。店主でもある、屋部龍馬さんと、武山忠司さんだ。レシピを考える際には気をつけていることがあると、屋部さんが教えてくれる。
「甘すぎないことですね。いわゆる和菓子って、甘すぎるのが敬遠される理由なのかなと。うちのは1つ食べても満足するんだけど、なんだったらもう1個イケるよみたいな」
たしかに、ここのお菓子は甘党やあんこ好きを十分に満足させるが、甘いものが少し苦手な男性にも食べやすいに違いない。そんな絶妙な加減だが驚いたことに、二人とも和菓子店での修業を一切していない。そのせいだろうか、和菓子といえば、伝統や暖簾を守るという堅いイメージがあるけれど、羊羊の場合はそれらに縛られていない分、自由な伸びやかさを感じる。
例えば、アレンジしたどら焼き“もちどら”には、皮と餡の間に生餅と、なんと砕いたカシューナッツが挟まれているし、そもそも和菓子屋といっても和のお菓子にとらわれていない。琉球菓子である冬瓜漬や、台湾のちまきがあったりする。
和の趣の落ちついた店内でありながら、そのラインナップが不自然でないどころか、思わずニヤリとし、ワクっとする。台湾からの観光客には不思議がられるというが、台湾ちまきをメニューに加えたのは「ただ単に好きだから」。こんな遊び心が、胸を踊らされる理由だろう。


そもそも、羊羊が誕生した経緯が面白い。
“机”という屋号でデザイナーとして活動する武山さんが、「お客さんと直に接する仕事もしてみたい」と物件を探していたのが始まり。友人でそのことを知っていた屋部さんが、この場所を見つけてきた。また屋部さんも、広さが十分にあり、駐車場のスペースもあるこの物件を気に入った。折しもオーナーを務めるカフェ、プラウマンズランチベーカリー(関連記事)をスタッフに任せられるようになっていたというタイミングもよかった。
「じゃ、借りる? 一緒にやる? 何やる?」
そんな軽やかな様子で、二人の相談が始まる。当初は家具屋や器屋、ゲストハウスなどが候補としてあがっていたそう。けれど、武山さんの一言で、方向がすんなりと決まった。
「『あ、和菓子屋やりたい。きっと楽しい』って。僕の実家は、岐阜で和菓子屋をやっていたんです」
ああ、いいかもね、と屋部さんもあっさり同意。和菓子屋というのが一番しっくりきたそうだ。

武山さんのご実家は、曾祖父様が昭和元年に和菓子屋を始めた。2代続いたが、お祖父様の代で店を閉めたそう。
「家にこんな道具がまだ残っているなんて知らなくて。和菓子屋やろうと決めて実家に帰ったら、物置に当時の道具が色々と残っていたんです」
菓子を並べる木箱である番重、あんこを炊く銅製の大きな鍋、それを混ぜる木製のヘラ。曾祖父様、お祖父様が使っていた約100年前の道具を持ち帰り、この店で使っている。銅製の鍋で炊くあんこは、他の鍋で炊いたそれとは全く味が異なるとは、屋部さん。
「小豆の芯までほっこりと柔らかく火が入るんだけど、煮崩れないんですよね」
調理道具だけではない。大小様々な落雁の木型は、店の大切なインテリアになっている。

さて、和菓子屋をやると決まったけれど、もちろん二人とも和菓子を作った経験はない。けれど、レシピ開発に臆することはなかった。
「はい! 僕、大福つくりたい!」「じゃあ、俺、どら焼き」
こんな調子でそれぞれ、つくりたいお菓子を試作をすることに。もちろんすぐに美味しいものができたわけではない。屋部さんが、思い出し笑いをする。
「最初は、ものすごーく塩っぱい大福が出来上がったり(笑)。ちょうどお店の内装工事が遅れたので、半年くらいかけてゆっくり試作できました」
完成するまでさぞや大変だったのでは?と聞いてみても、「いや、そんなに」と、二人とも苦労を感じさせない。そもそも羊羊という店名は、二人が同い年で未年生まれだから。羊のように、二人はとても穏やか。ただただ、今の新しいチャレンジを楽しんでいる。

武山さんは、自身のルーツを感じるのが楽しいそう。
「両親が共働きだったんで、小学校が終わったら毎日、おじいちゃんおばあちゃんのいるお店へ帰っていたんです。そこで遊んだり、お店を手伝ったり。もちろんその記憶はあるけれど、和菓子屋始めるなんて少しも思ったことなかった。でもこの店をやってみたらすっごい楽しくて。自分のルーツに触れられているからですかね。幼い時は、なんにも感じていなかったけど、おじいちゃんは、ちっちゃい僕とか姉とかが遊んでる店で、毎朝あんこ炊いて、まんじゅう包んでたんだな。そういう当たり前の日常の中で、何を考えながらあんこ玉丸めてたのかなとか、考えるのが楽しいんです」
一方屋部さんは、プラウマンズランチベーカリーとの違いが新鮮なよう。
「あっちの店では、僕が全部決めなきゃいけないけど、こっちでは、僕が全部を決めなくていいっていうね。責任者だけど、自分だけが主導するんじゃない。自分と同じテンションで、同じくらいやってくれる人がいるっていうのがすごい強みで。例えば僕が全部『こうでなきゃ』と言ってしまうと、結局プラウマンズと同じような店になってしまうでしょ。あえて武山君にまかせたら、このお店はどうなっていくのかなという、楽しい実験をしている感じ。僕は、武山君のセンスを信用してるんで」
現に冬瓜漬、台湾ちまきは、武山さんのアイディアから商品化されたもの。日持ちのする冬瓜漬はお土産として喜ばれ、台湾ちまきは小腹の空いたお客に重宝されている。

店主の武山忠司さん(左)と、屋部龍馬さん(右)。
こんな風に二人の発言にそこはかとない余裕を感じるのは、二人が40という成熟した年齢で、既に核となる別の仕事を持っているからだと気づく。何が何でも、という気負いがないし、2つの仕事に違いがあるからこその刺激を純粋に楽しんでいるのだろう。
今後は1年を通して、季節を感じる和菓子を発表していくそう。桜の季節には桜餅、端午の節句には柏餅というように。今後について屋部さんは、「目標なんてないけれど」と前置きして教えてくれた。
「これまでと変わらず、シンプルなんだけど、家庭でできないものをつくっていきたいですね」
一方、武山さんも目を輝かせる。
「沖縄のお土産として使ってもらえるようなお菓子をつくりたいです。何か新しいお菓子がここで生まれたら嬉しいですね」
この店には、広い広い土間がある。何もなくただ広がる静かな空間。この空間のように羊羊のこれからは、予想できない余白があって伸びしろがある。
写真・文 和氣えり

羊羊 YOYO AN FACTORY
北中城村喜舎場366
098-979-5661
open 10:00~17:00
close なし
https://yoyo.okinawa
https://www.instagram.com/yoyo.okinawa/