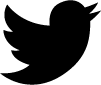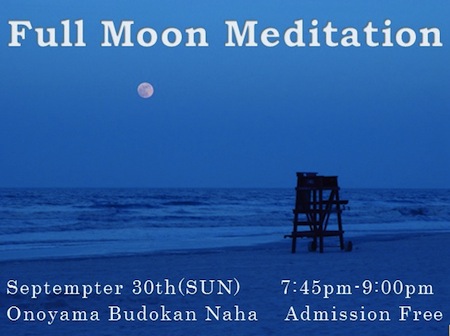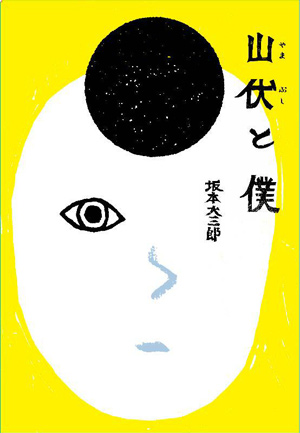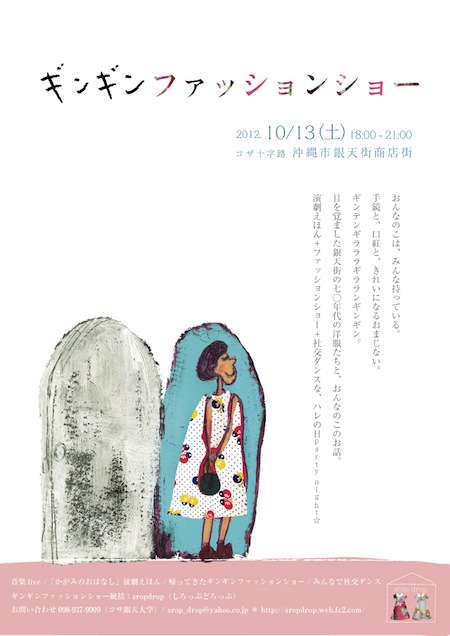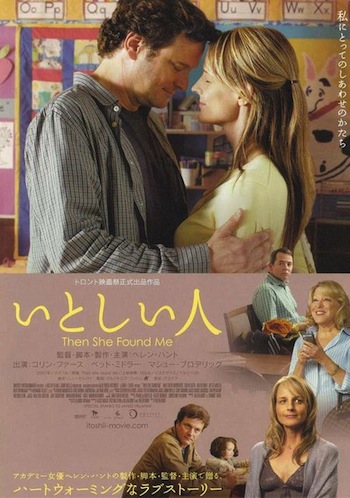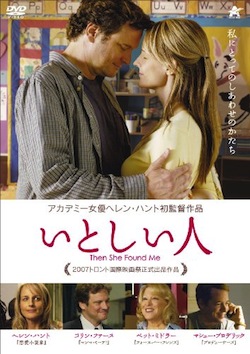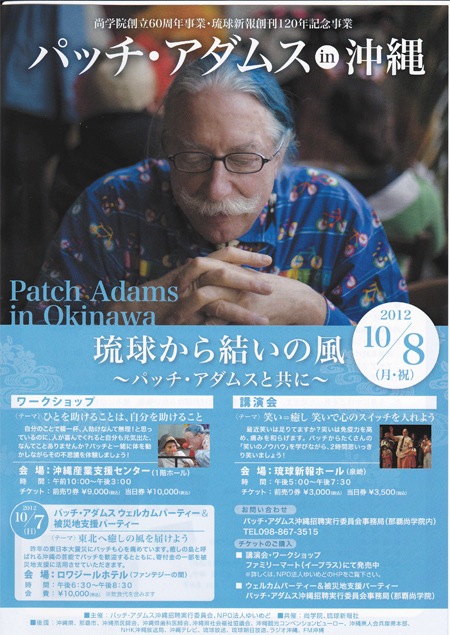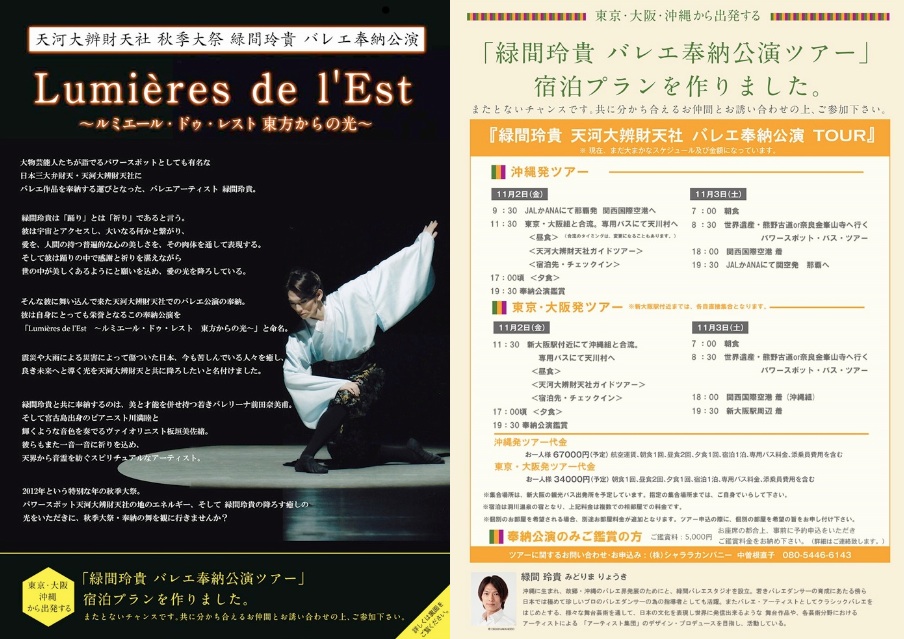「タガネ」と呼ばれる工具を使い、細かな目をひとつひとつ職人が手仕事で掘り起こしたおろし金。実際におろしてみればその違いは明らか。職人の技によって生み出される銅手打ちおろし金は、細胞をやさしく壊すことを可能にするため、繊細にして豊潤なおろしができあがる。秋の訪れにふさわしい静かな温かみと、春の光に映える花のつぼみのようなフォルムを同時に有するランプシェードは、陶芸家・小谷田(こやた)潤氏の作品。
道具や雑貨のむこう側に見えるのは、豊かなくらし。決して派手ではないが、本当の豊さに導いてくれるものだけが並ぶ。
便利さやスピードを追求しただけの、味気ないモノはどこにも見当たらない。
たとえ「それ」が無くても生活はできるし、むしろもっと安価で手に入る類似品は山ほどある。でも、「それ」があると心持ちが変わる、何気ない日常が優しい色を帯び、くらすことが愛おしくなる。
例えば水分をたっぷり含んだまろやかな大根おろしや、食卓を包むやわらかな光の力によって。





雑貨屋「カタチ」は、本部(もとぶ)町のひっそりとした山の中に静かにある。
オーナーの岸名美由紀さんを、県内で開かれる市で見かけたことがある人も多いのではないだろうか。カタチをオープンさせる前は、ドリンクメニューがメインの移動販売店「kishina-ya」を夫婦で運営していた。
「ずっと雑貨店をやりたいとは思っていたのですが、なかなかいい物件が見つからなくて。ターゲットを本部にしぼって物件探しを続けながら、見つかるまでの仕事として移動販売を始めたんです」
ふるさとの三重県から沖縄に移住したのは6年前。美しい海に魅せられたのがきっかけだった。
「私も主人も南の島が好き。沖縄に移住する前は、バリ、プーケット、モルディブ…と、やはり南の島ばかりを旅行していました。初めて訪れた沖縄で素潜りを体験し、沖縄の海の美しさにすっかりハマってしまったんです。海への思いは今も変わりません。店の昼休みを利用して、瀬底ビーチなんかにさっと潜りに行くこともよくあるんですよ。のんびりと泳ぐ魚を見ていると癒されるし、海に入ることで心も体もリセットされる感覚があるんです」
移住後約一年間は沖縄の海を堪能すべく、ただただ泳いでばかりいたが、次第に仕事への意欲にかきたてられるようになった。
「沖縄ってそういう意味でも不思議な場所、土地にエネルギーがある気がします。『何かやりたい!』って思わせてくれる」


その頃、美由紀さんは友人から「手づくり市に参加しないか」と誘いを受けた。
「アンティークビーズを使ったアクセサリーを作って出店したら、想像以上にお客様に気に入っていただけて。それがすごく嬉しかったんですよね」
雑貨屋をやりたいという想いに拍車がかかったが、希望通りの物件が見つからず、バーテンダーとして飲食店勤務の経験もあったご主人とともに、移動販売を始めることにした。
「あくまでも、雑貨店を始めるまでの仕事と考えてスタートさせました」
美由紀さん夫妻が探していた物件の条件は、店舗兼住居として使え、駐車場があり、敷地内に畑があること。すべての条件を満たす希有な物件に出会えたのは実に、探し始めてから4年が経過したころだった。それを境に、2年間営業を続けた移動販売「kishina-ya」の看板をおろし、「カタチ」をオープンさせた。



オープン当初、美由紀さんの中には確固としたコンセプトは特になかったと言う。
「自分が欲しいものを置こう、と。考えていたのはそれだけ(笑)。でも、本部の自然に囲まれて過ごしているうちに、価値感や考え方が徐々に変わってきて。自然の偉大さを感じるようになったし、すべてが繋がっているのだと気づいたんです。それで、お店で自然を提案したいと思うようになりました。オープン当初と比べると、店の方向性はだいぶ変わったと思います」
美由紀さんが心惹かれるアイテムに共通しているのは「作り手の心が感じられるもの」。
「服や雑貨そのものというよりも、その後ろ側にいる作り手さんに惹かれるのだと思います。最近は、自然について考え、しっかりとした理念を持ってモノづくりにあたっている作家さんの作品を扱うことが増えました。例えば『而今禾(jikonka)』もそう。草木染めのオーガニックな服を作り続けているだけでなく、無農薬野菜を使用したランチを提供するカフェも開いていて、また、オーナーの米田恭子さんは台湾で途絶えた機織りの復興活動にも尽力なさっています。作り手さんのそういう熱い思いに触れると、どうしてもその方が作るものに惹かれますね」
アパレル業界での経験も豊富な美由紀さんだが、本部で暮らすようになって服の好みにも変化が生まれたと言う。
「昔から洋服は好きなのですが、ここ最近は『働きやすい服』が好き。徐々に機能重視にシフトしてきたんですね。而今禾の服はゆったりめのラインの服が多くて動きやすいですし、ポケットが多かったりと、働く人にぴったり」



「pota」の靴。「三重のギャラリーで試しに履いてみたら、足にぴったりと吸い付いてくるような感触が素晴らしくて」

奔放なタッチに愛嬌のあるフォルム。しかし、器全体からは静けさが漂う独特な佇まいの作品は小泊良氏の作品。
昔から好きだった洋服とは違い、器に興味を持つようになったのはカタチをオープンさせてからだと言う。
「いかにも自由な作風に惹かれたんです。その場の発想で描く、スピード感を感じさせるデザインが好きで」
料理は決して得意ではないと笑う美由紀さんだが、バナナ、マンゴー、パパイヤを使ったシャーベットをふるまってくれた。
「それぞれの果物をカットして凍らせたものをミキサーにかけただけ」
美しい器に盛られた、素朴な甘さとさわやかな酸味が嬉しい完全無添加のシャーベット。美由紀さんのかざらない、自然とともにくらす豊かなライフスタイルの一端に触れ、羨ましさと同時に、かすかな懐かしさも覚えた。


昔はもっと、色んなことがシンプルだった。暗くなれば店は閉まり、家族は家で食卓を囲んだ。
かつお節を木製の削り器で削るのが私の役割だった。ボイラー設備は整っていたが、我が家ではできるかぎり木をくべて風呂を湧かしていた。火を絶やさぬよう、寒空の下で薪を窯に入れるのを見るのが好きだった。
家庭用のゲームが販売されて爆発的な人気となっても、ゲームにはないダイナミックさを楽しめる外遊びは依然楽しかった。野原でやる野球、れんげ畑でのかくれんぼ、大量のガマの穂を綿状にほどき、プールに見立ててジャンプ!
そばにはいつも自然があった。
日付を越えるまで起きていることはなく、夜の虫の声に包まれて眠った。風が吹けば潮の匂いを感じた。玄関から一歩出ると必ず、その季節特有の香りに包まれた。
自然とともにくらす。それはなんと贅沢なことだったのだろう。
様々な不幸が日本を襲った今、心からそう実感する。


アイアンと木材の組み合わせが美しい椅子はご主人の手製。広々とした店内も住居部分も、その改装は夫婦二人でおこなった。什器はほぼすべてご主人作。「元はグラフィックデザイナー。鉄を扱う仕事などを経て今はハルサー(笑)。なんでもできちゃう人なんです」。カフェやショップなどから依頼を受けて什器を製作することも多い。

洗濯、食器洗い、シャンプー。洗うものすべてに使える松の樹液で作られた「マツノチカラ」。「実は、当店イチオシの商品はこれ。空のペットボトルも用意していますので量り売りもできます」
美由紀さんが今後力をいれたいのは畑仕事だというのを聞いて、思わず微笑んでしまったが、その言葉はストンと腹に落ちた。美由紀さんが選び抜いたモノたちに囲まれているせいか、その思いが店の空気にも溶けていて自然と伝わってくるからだ。
「目指せ自給自足! とばかりに夫が中心となって畑をやっているんです。今は野菜を主に育てているのですが、いずれはカタチで販売できたらなと考えています。震災以降、食材に対する心配の声は高まっていますから、安全なものを提供できたらと。目指せ八百屋さん!…いや、よろず屋かな(笑)。自然をテーマに、自然に優しいものであれば何でもアリかな〜って(笑)」
耳を澄ませば陽光が降り注ぐ音さえ聞こえてくるのではないだろうかと思うほど、静かな場所。美由紀さんは今、色々な電化製品を手放すことにハマっているのだと言う。炊飯ジャー、電子レンジ、ドライヤー。
ここにはなにもない?
それとも、すべてがある?
ぜひその目で確かめて、感じてほしい。
写真・文 中井 雅代

暮らしの道具店 カタチ
本部町字伊豆味2830-1
0980-47-5307
営業日 金・土・日・祝日
営業時間 12:00-17:00
HP http://catachi-plus.com
ブログ http://blog.catachi-plus.com