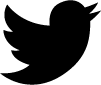「フランスの本屋では、料理本はアートのコーナーに置かれているんですよ。街ではシェフが、アーティストみたいにサインをねだられることもあります。フランス料理は、見た目の美しさも食材の組み合わせ方も、アートですね。そんなフランス料理を、肩肘張らずに普段着で楽しんでほしくって」
これが、ビストロ「モンマルトル」のオーナー、植村愼太朗さんがお店を開いた理由だ。
料理がアート? 一度味わってみれば、きっと誰もがその意味を理解する。

『サーモンマリネと帆立貝のタルタル サラダ仕立て ビーツのヴィネグレットソース』

『フランス産フォアグラのキャベツ包み蒸し
ラビオリ仕立て 黒トリュフ風味 カプチーノ風』
アートといえば、分かりやすいのは見た目の美。確かにどの皿も、ソースの一滴の置かれ方にさえも意図が感じられる。
特に、目を奪われたのは、「サーモンマリネと帆立貝のサラダ」。彩りと形の繊細さは、フォークを入れるのをためらうほど。
透明なお皿も、海の幸を味わうにぴったりの風情。フランス料理といえば真っ白な丸皿のイメージだが。
「その土地の特長あるものと上手く調和させるのもフランス料理なんです。だから器も、ここ沖縄の、やちむんを使ったりもしますよ。紅茶はやちむんでお出ししています」
また、食感が新しいのは、「フランス産フォアグラのキャベツ包み蒸し」だ。キャベツを一口噛めば、想像もつかなかった脂の旨みが艶やかに弾ける。
食感もアートになるのかと驚く。
「実は、これ、蒸しているんです……」
植村さんが打ち明けるような口ぶりで教えてくれた。
「蒸すという調理方法は元々、東洋のものでね、フランス料理にはなかったんですよ。2~30年前に、鬼才と呼ばれたアラン・サンドランスが三つ星レストラン『ルカ・キャルトン』で取り入れたのがきっかけだったんです。テリーヌもポワレも脂を落とす調理方法なのに対して、これは脂をまるごと包み込む。全てを味わえる小籠包のような面白みがありますね。そこに、さらに僕のアレンジを加えて、カプチーノ仕立てにしています」
また、これは植村さんのスペシャリテでもある。スペシャリテとは、季節に応じて作られるシェフの得意料理、その店で味わうべきものの意味。スベシャリテも納得の、植村さんの個性と自信を感じる一皿だ。

『特選国産牛フィレ肉のソテー フランス産フォアグラのポワレ
季節の野菜添え トリュフソース ~ロッシーニ風~』
見た目の美しさや食感も確かにアートだが、なんといっても味にこそ、アートを感じたい。メインに据えられた「牛フィレのソテー」は、その期待を裏切らない。
「これには贅沢に、世界三大珍味のうち二品、フォアグラとトリュフを惜しみなく使っていて、ソースはトリュフとマデラ酒とフォン・ド・ボーを煮詰めた伝統的なソースです。フランス料理には『ロッシーニ風』と付く料理が多いんですが、これもその1つですね。ロッシーニというのは作曲家ですが、大の食通としても知られていて、彼の愛した料理ということです」


『ズワイガニと白身魚のクレピネット包みロースト
エピス風味 シェリー風味のジュ・ド・クリュスタッセ 森の木の子たちを添えて』
貴重なクレピーヌ(豚の網脂)を使って炙り焼きしている
アートの域にまで昇華された植村さんの料理。それを引き立たせるワインにも、もちろんこだわりがある。店に並ぶワインのほとんどが、農薬を使わずに育てたブドウを自然発酵させたヴァン・ナチュールだという。そう言われれば赤色が少し薄く、香りもほのかだ。
「できる限り、自然な形で作り上げられたワインは、酸味やクセもそのまま残りますが、果実本来の味わいを楽しめますよ。それに、二日酔いになりにくいんです。もちろん僕も、料理に化学調味料を一切使わないし、料理もワインも優しさにこだわっています」
植村さんが、「僕の右腕でもあり、左腕でもある」と信頼を寄せる、ソムリエ兼店長の依田さんが集める充実のセレクト。ワインだけでも楽しめるようにと、店は、毎夜21時からはワインバーとなる。

『アミューズ・ブーシュ ~自家製パンに島豚のリエットを付けて~』
天然酵母を使った素朴な味わいのパンと、肉の力強さが活きたリエット
植村さんの料理は、一皿一皿に使われる食材が見た目よりもずっと多い上に、たった1皿を完成させるために何工程もかかっている。添えられたソースでさえ、何種類もの材料を、何時間もかけて煮詰めていく。惜しみない手間の賜物だ。
「奥深いでしょう? これこそが僕がフランス料理に魅せられた理由なんです。1つ1つの細やかな積み重ねが1皿になっていくというのが……。手順だけでなく、料理方法も幅広いですよ。例えば、フォン・ド・ボーひとつとっても、骨を焼く・焼かないから始まって、焼き加減や野菜は何を、どれぐらい入れるか……と、実に千通りもの作り方があるんです。どうやって1皿を作りあげていくかが本当に深くて、しかも正解はないんです。終わりもない。面白いですね」


日本では、ここでしか味わえないティー・バイ・テ。アール・グレイ、ダージリン、ブルー・リラックスの3種
また、料理方法だけでなく、背景や歴史にも魅せられるという。
「その料理が、どんな経緯で生まれた料理なのかを知れば知るほど面白くって。先程のロッシーニもそうですが、歴史上の有名人の名前もどんどん出てきますよ。ナポレオンがロシア遠征の際に作らせた料理なんていうのもあったり…」
その口調からは、フランス料理への深い愛を感じるが、植村さんがフランス料理人の道を歩み始めたのは、それ以外の理由もあった。
「僕の父は、中華料理の料理人だったんです。料理人の家ということもあって、食卓にはいろんな料理が並んでいましたね。ただ、毎日帰りは遅いし、父から漂う油の匂いも嫌いでした。でも、僕も18才で進路を考えた時に、他人より自信を持てることって、やっぱり味覚しかなかったんです。給食でも外食でも、使っている食材やダシが当てられたんですよ。でも、そこはまだ18才で、父親への反発や、カッコよさそうという理由で中華でなく、フランス料理を選びました。もちろん、色々食べ歩いた中で『フランス料理が一番美味しい!』と感じたのもありますけど」
タカマツ、キハチ、ビストロダルブル……都内の有名店で修業を積み、25才の時に本場のフランス料理を学ぶため、パリへ渡る。

季節のチーズの盛り合わせ。チーズにも季節があるのだとか
「フランスの料理界には、求人募集の貼り紙なんてものはないんです。紹介か、自分自身で売り込むしかない。だから、あちこちのレストランを食べ歩いて、自分でも『美味しい!』と思えたレストランで、食事後に『シェフを呼んでください!』とシェフを呼びだして、直に雇ってほしいとお願いしました。そのために『シェフを呼んでください』のフレーズだけは、日本にいるうちに完璧に言えるようにしておいたんですよ」
そこは、パリで最も忙しいとされる人気のお店「レガラード」人手はいくらあっても足りず、運良く採用となったが、それからが苛酷な日々だった。
「技術よりも、言葉の壁が想像以上でしたね。日本にいる間も語学学校には通っていたんですが…。でも中学3年間、英語を学んだって喋れないし、それと同じかもしれませんね。悔しかったですよ。同僚に、『あのジャポネ(=日本人)のせいだ!』と言われても、何も言い返せないし、厨房でポツンとすることもありました。もう1年目はノイローゼになりかけました……」
だが、目指したフランス料理を身に付けるまでは帰れない。植村さんは懸命に努力した。
「フランス人は凄くクセのある字を書くので、解読するために、店で処理済みの伝票を持ち帰って読んだり、会話で分からない単語があれば、ノートに書いておいて後で調べたり、空き時間に語学学校へ通ったり、とにかく必死でした。そのお蔭か、1年が経つ頃には、『ジャポネの洗い物は洗わないぞ!』と嫌がらせされても、まだ手つかずの皿もまとめて洗い場に投げ込んで、『洗えよ! 洗い物を洗うのがお前の仕事だろう!』と怒鳴り返すぐらいには成長しましたね(笑)」
そして、植村さんに最も大きな影響を与えたピエール・ガニェール氏に師事することとなる。ピエール・ガニェール氏はミシュランの三つ星を獲得し、その独創的な料理から、厨房のピカソと呼ばれているシェフだ。各国に店舗を展開し、世界中に根強いファンを持つ。
「ガニェール氏の元で働けたのは、運も良かったですね。彼は、画期的な食材の組み合わせをするんです。たとえば、普通は海のカキとフォアグラを合わせるなんて想像つかないでしょう? そういった発想やセンスにすごく影響を受けました」


多くの収穫を得たパリでの修業を終え、帰国後は、東京のオザミトーキョーで8年間働き、沖縄へと活躍の場を移した。なぜ、沖縄だったのか。
「妻が那覇出身で、沖縄は馴染み深い場所でした。ブセナテラスから誘いもあり、沖縄行きを決意したんです。それに、地方から美味しいものを発信したいとも思って。日本では、どうしても東京中心ですが、フランスでは、パリ以外の地方にも三つ星のレストランはたくさんあって、美味しい食事を求めて人が動くんですよ」
実は、沖縄はフランス料理を表現するにはうってつけの場所なのだという。
「“テロワール”という言葉が、フランス料理にあります。その土地の、特色ある食材をうまく活かすという意味ですが、沖縄はその点で恵まれていますね。まず、沖縄と南フランスは、太陽の恩恵を強く受ける気候が似てるんです。野菜も、良く言えば力強い、悪く言えばエグミがありますが、南フランスの料理の再現がしやすいです。それに、沖縄は海の幸も良いですよ。たとえば、ウニは、北海道のバフンウニよりも沖縄のシラヒゲウニの方が甘くて、美味しいぐらいです。魚だって、『白身ばかりでブヨブヨしてる』なんて言う人がいますが、うまく料理すれば、内地の魚よりずっと美味しいです。また、トリュフなどはフランスから輸入するんですが、沖縄は羽田空港からの便数が多く、地方の中でも有利な条件が揃っていて、毎日新鮮な食材が手に入ります」
ブセナテラスでは、国際会議の場で各国首脳に出す料理を手がけるなど、腕をふるっていた植村さんだが、そのうちに危機感を覚え始める。
「このままでは日本のフレンチはダメになると思って……。日本では、フランス料理ってイタリアンみたいには浸透してないでしょう? ブセナテラスでは、どうしても記念日などの特別な料理しか作れない。敷居の高い場所じゃなくて、もっと気軽に、日常的に味わえる料理をやりたくなって。だから、ビストロです」
そんな想いから、2012年12月、那覇市真嘉比に「モンマルトル」をオープンさせた。モンマルトルは、植村さんがフランスで住んでいた思い出の土地だ。
「初めは不安でした。周りからも『沖縄でフレンチなんて流行らないよ!』って散々言われたんです。でもフタを開けてみれば、お客様がたくさんで。僕の願い通り、地元の方が気軽に来てくださるのが一番嬉しいですね」

植村さんは、どの場所にいても、追い求めていることがある。
「僕のテーマは、“記憶に残る料理”なんです。家族や恋人、友達と楽しい食事をした時って、料理はただ、『美味しかったね』だけで終わってしまいがちですよね。そうじゃなくって、『あの時の、あの料理がまた食べたい!』と覚えていてもらえるような料理を、僕は目指しています。そのためには五感に訴えて、強く印象を残さないといけない。だから味覚、視覚、嗅覚はもちろん、紙包みを手で破って中の物を食べるなんていう、手の感覚を使うような料理も作っているんですよ」
フォアグラの包み蒸しや、フィレ肉のソテー・・・初めにつまんだパンにいたるまで、しっかり記憶に残っている。いろいろ、次々に出てきたのに、そのすべて、またあの味に会いたいと鮮明に思い出し、焦がれる自分がいるのだ。
アートとは、表現で感情を動かすことだとしたら、植村さんの料理は確かにアート。五感を揺らし、刻みこんで離れない。

le Bistro Montmartre (ビストロ モンマルトル)
那覇市真嘉比1-1-3 エリタージュK 1階
(2階に3台分 駐車場あり)
098-885-2012
OPEN
Lunch 11:30 ~14:00(L.O.)
Dinner 18:00 ~21:30(L.O.)
Wine Bar 21:00~24:00(Close)
CLOSE 月曜日
HP http://montmartre.ti-da.net
FB https://www.facebook.com/bistro.montmartre
文 石黒万祐子