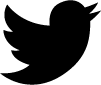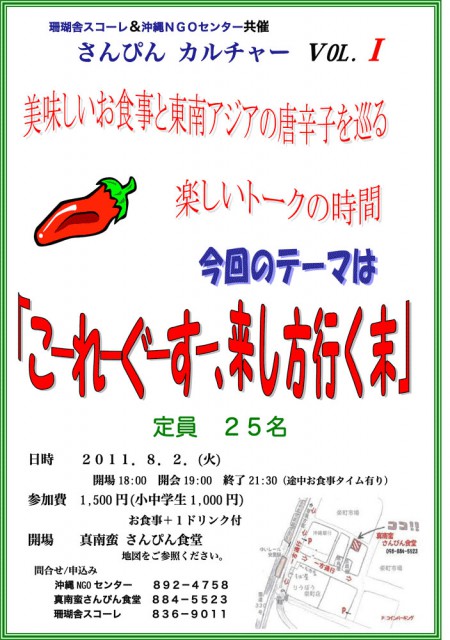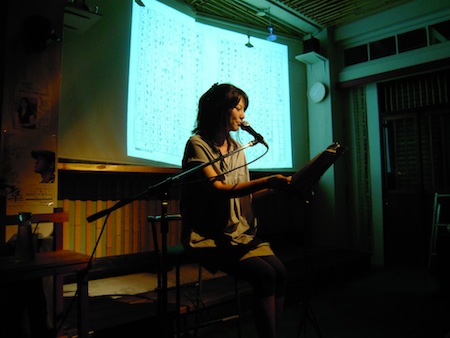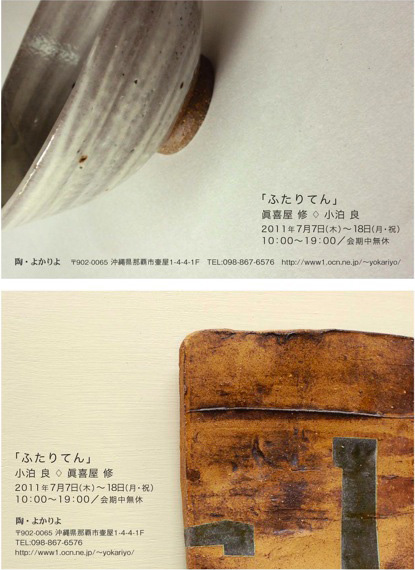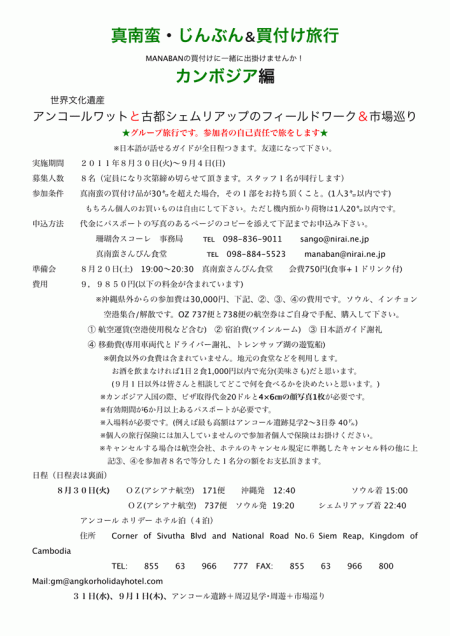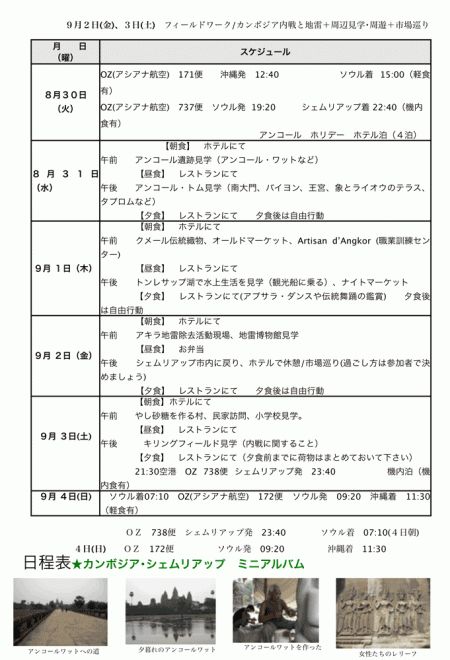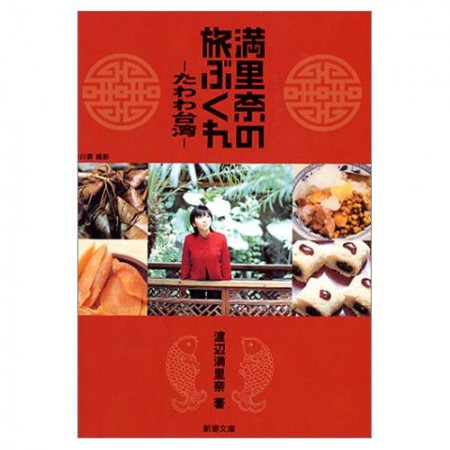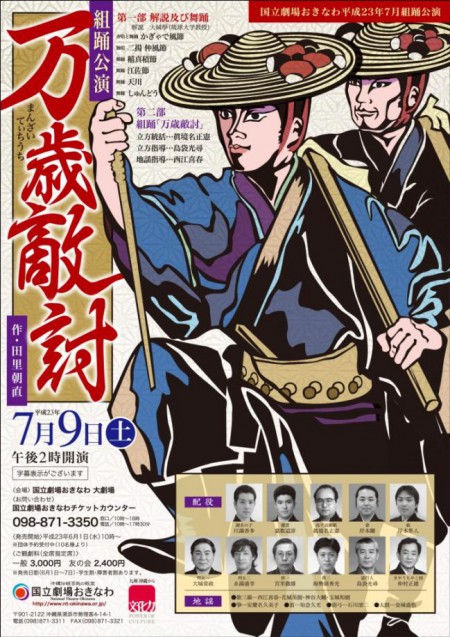出場のお申し込み、始まってます!

【第3回沖縄キッズトライアスロン大会inうるま】
開催日:2011年7月31日(日)
開催場所:海中道路ロードパーク
参加費:【個人部門】6,000円 ※保険料含む ※ファミリー割引(同じ家庭内,2人以上の参加により,2人目から5,000円)
【リレー部門】9,000円(チーム) ※保険料含む ※スイム1人,バイク1人,ラン1人 計3人で編成する
申し込み期間:2011年6月1日~
申し込み方法:参加申込書,誓約書に必要事項を記入,押印の上,参加費振込書の写しとともに,事務局宛に郵送する。必要書類すべてが揃わないと参加受付できない。参加申込書及び誓約書は各ホームページにてダウンロードしてください。
うるま市商工会▶http://www.uruma-shoko.jp
うるま市商工観光課▶http://www.city.uruma.lg.jp/5/4617.html
沖縄県トライアスロン連合▶http://otu.majun.jp/
沖縄タイムス社▶http://www.okinawatimes.co.jp/
競技内容
制限時間:全種目共通12:00
定員:各学年50人(計450人)・リレー部門各10組(計120人) ※先着順 男女混合
参加資格:レース当日健康な小学1年~6年,中学1年~3年の児童生徒
競技方法:自転車はヘルメット着用のこと
※水泳はウェットスーツ推奨,給水はランコースのみ
表彰:【個人部門】男女別学年別総合1位~3位(賞状授与)
【リレー部門】カテゴリー別チーム総合1位~3位(賞状授与)
申し込み先・問い合わせ
沖縄キッズトライアスロン大会inうるま実行委員会事務局
〒904-2427 沖縄県うるま市与那城屋平4番地先
TEL:098-978-0077 FAX:098-978-1177
※7月24日(日)に初心者対象の「トライアスロン教室」を開催します。参加希望者は、申し込み用紙に明記すること。
主催:うるま市観光物産協会
共催:沖縄タイムス社
特別協力:沖縄トライアスロン連合
後援:沖縄県,沖縄コンベンションビューロー,うるま市,うるま市教育委員会,うるま市商工会,琉球放送,琉球朝日放送,FM沖縄,FMうるま
大会ボランティアスタッフも募集中!
大会当日は会場の模様をFMうるま86.8MHzで生中継いたします。